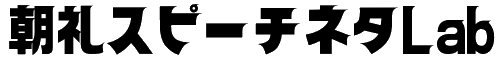柿の木
皆さん、おはようございます。
朝晩が少しずつ肌寒く感じられるようになり、秋の気配が深まってまいりました。
今日はそんな秋にまつわる、少し情緒のあるお話をさせていただきたいと思います。
かつての日本の家屋のそばには、必ずと言っていいほど柿の木が植えられていたと言われています。
子どもの頃、祖父母の家の庭先に大きな柿の木があり、秋になると枝がたわわに実をつけていた、そんな風景を思い出される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
赤く色づいた柿の実が、まるで収穫の時を待っているかのように揺れている光景は、私たち日本人の心の中にある「原風景」と言えるのかもしれません。
秋の果物といえばリンゴや梨もありますが、柿は特に俳句や短歌といった文学の中で、秋を象徴するものとして多く詠まれてきました。
その中でも私が特に印象に残っているのが、明治時代の俳人・正岡子規が詠んだ一句です。
「柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺」
これは、旅先の奈良で柿を食べていた子規の耳に、ちょうど法隆寺の鐘の音が響いてきて、その瞬間の感動を詠んだ句です。
特別な技法や難しい言葉は使われていないにもかかわらず、その場の空気や音、そして柿の甘さまでが伝わってくるような、なんとも味わい深い一句だと私は感じています。
この句の良さは、「何も起きていない日常」を丁寧に味わっているところにあるのではないでしょうか。
忙しい日々の中で、目の前の仕事やノルマをこなすことに追われていると、ふと立ち止まって「今この瞬間」を感じる余裕がなくなりがちです。
しかし、たとえば昼休みに飲む一杯のコーヒーや、帰り道に見上げた空、道端の金木犀の香り。
そうした一瞬に「季節」を感じたり、「ああ、秋だな」と思えたりすることが、心の豊かさに繋がっていくように思います。
正岡子規のように、日常の中の何気ない風景に心を留めること。
そして、それを味わうゆとりを持つこと。
それは、仕事をするうえでも実はとても大切な姿勢ではないかと私は思っています。
「余裕があるからこそ、よい仕事ができる」とも言えますし、感受性を持って物事を見られる人は、細やかな気配りや配慮にも長けていることが多いと感じます。
秋は、自然が一段と表情豊かになる季節です。
皆さんもぜひ、柿の実の色づきや、秋の空の高さ、風の匂いなどを感じながら、日々の忙しさの中にも心のゆとりを見つけてみてください。
ありがとうございました。
しっくりくるスピーチが見つからない方へ
テーマを入力するだけで、あなただけのスピーチを作成してくれるツール「AIスピーチジェネレーター」を作成しました。
もう原稿作りに悩まない。AIスピーチジェネレーターは、あなたのアイデアを言葉に変える相棒です。
まだベータ版ですが、今なら誰でも無料・登録不要でお試しいただけます!