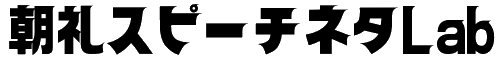花火大会
皆さん、おはようございます。
本格的な夏を迎え、夜空に大輪の花が咲く季節になりました。
今日は、「花火大会」についてお話ししたいと思います。
日本最初の花火大会は、隅田川花火大会と言われていて、その起源は江戸時代、享保14年、西暦でいうと1732年にまで遡ります。
その年、日本では大飢饉が発生し、多くの人々が飢えや貧困に苦しみました。
さらに疫病が流行し、被害は一層深刻なものとなりました。
まさに世の中が不安と絶望に包まれていた時代です。
翌年、八代将軍・徳川吉宗は、その犠牲となった人々の御霊を慰め、また悪疫退散を祈るために「水神祭」という祭事を行いました。
その際、両国橋付近の料理屋が幕府の許可を得て花火を打ち上げたと言われています。
これが、現在の隅田川花火大会の原点とされ、「両国の川開き」と呼ばれていたそうです。
もともとは慰霊と鎮魂、そして人々に少しでも明るさを、という願いが込められていたんですね。
それが今では、夏の風物詩として多くの人に楽しまれるイベントとなりました。
花火と聞くと、私たちはつい華やかさや美しさに目を奪われがちですが、その背景には、先人たちの悲しみや祈り、そして希望の思いが込められているということを忘れてはならないと思います。
また、地方によっては花火を「迎え火」や「送り火」として、亡くなった方々の魂を迎えたり見送ったりする意味を持たせている地域もあります。
戦災や自然災害で命を落とされた方々への慰霊の意味を込めて、花火を打ち上げるという話も耳にします。
夜空に大輪の花が広がる瞬間、私たちの心も高揚し、思わず歓声を上げてしまいます。
でもその美しさの奥に、平和な今を築いてくれた多くの人たちの歩みがあること。
そのことに思いを馳せながら、花火を見るというのも、大人としてのひとつの楽しみ方ではないでしょうか。
今年の夏、皆さんももし花火を見る機会があったら、ぜひそうした背景にも心を向けてみてください。
きっと、今までとは少し違った風景が見えるかもしれません。
ありがとうございました。
しっくりくるスピーチが見つからない方へ
テーマを入力するだけで、あなただけのスピーチを作成してくれるツール「AIスピーチジェネレーター」を作成しました。
もう原稿作りに悩まない。AIスピーチジェネレーターは、あなたのアイデアを言葉に変える相棒です。
まだベータ版ですが、今なら誰でも無料・登録不要でお試しいただけます!