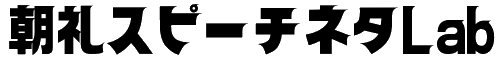初心忘るべからず
皆さん、おはようございます。
今日は、「初心忘るべからず」という言葉について、改めて考えてみたいと思います。
この言葉は、室町時代初期の能楽師、世阿弥(ぜあみ)が残した名言です。
私たちの多くは、「物事を始めた時の純粋な気持ちを忘れてはいけない」という意味でこの言葉を使っています。
それも確かに一理ありますが、世阿弥が著書『風姿花伝(ふうしかでん)』で語った本来の意味は、「何かを新しく始めるとき、人は不安や戸惑いを感じるが、それをどう乗り越えたかという経験こそが大切であり、それを忘れてはならない」ということです。
つまり、「初心」とは単なる初々しい気持ちではなく、「挑戦した時の自分自身との対話や成長の過程」を指しているのです。
私自身、仕事をしていて感じるのは、慣れてくると業務がルーチンになりがちで、いつの間にか「なぜこの仕事をしているのか」「どんな思いで取り組み始めたのか」を見失ってしまうということです。
ですが、ふと立ち止まって、「あのとき、自分はどんな思いでこの役割に挑んだのか」「最初の苦労をどう乗り越えてきたのか」を思い出すと、仕事に対する視点が変わることがあります。
世阿弥は、年齢や立場によって「初心」は常に新たに現れるものであり、常にそれを意識して自分を磨いていくことが、芸を深める鍵であると説きました。
これは私たちの仕事にも通じる考え方ではないでしょうか。
立場が変われば、求められるものも変わります。新たな挑戦に直面したとき、過去の経験やそこから得た学びを思い出すことで、次の一歩が見えてくることがあります。
「初心忘るべからず」。
この言葉の奥にある意味をかみしめながら、日々の業務に取り組んでいくことで、私たち一人ひとりの成長につながるのではないかと思います。
今朝はそんな思いを皆さんと共有させていただきました。
今日も一日、どうぞよろしくお願いいたします。
しっくりくるスピーチが見つからない方へ
テーマを入力するだけで、あなただけのスピーチを作成してくれるツール「AIスピーチジェネレーター」を作成しました。
もう原稿作りに悩まない。AIスピーチジェネレーターは、あなたのアイデアを言葉に変える相棒です。
まだベータ版ですが、今なら誰でも無料・登録不要でお試しいただけます!