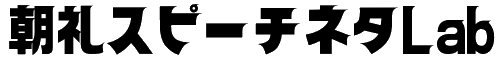「人生に失敗なんて存在しない。」
この一言から始まったスピーチが、どれだけ多くの人の背中を押したことでしょうか。
2019年3月23日、近畿大学の卒業式。登壇したのは、お笑い芸人・絵本作家・映画監督と、常に「型破りな挑戦者」として注目を集めるキングコング西野亮廣さんでした。
彼のスピーチは、単なる卒業祝いのメッセージにとどまりません。
登場の演出すらやり直すという“全力のボケ”から始まり、好感度の低さを自虐し、友人たちとの失敗談を笑いに変えたあとに、深く、静かに、こう問いかけてくるのです。
「僕たちは今この瞬間に未来を変えることはできない。
でも、過去を変えることはできる。」
笑いに包まれた会場が、最後にはしんと静まり返る。
「挑戦することの意味」「失敗の定義」「報われない時間をどう過ごすか」——。
これらを、ユーモアと共に真正面から語りかけたスピーチは、学生だけでなく、すでに社会で働く大人たちの心にも深く刺さりました。
この記事では、そんな“伝説の卒業スピーチ”の核心にあるメッセージを改めて読み解き、私たちが日々の仕事や人生にどう活かせるのかを考えていきたいと思います。
スピーチ動画(近畿大学公式YouTube)
スピーチ全文は、西野さんのブログで公開されています▼
https://ameblo.jp/nishino-akihiro/entry-12449260616.html
西野亮廣の人生そのものが“挑戦の実例”
西野亮廣さんは、もともとお笑いコンビ「キングコング」としてテレビの第一線で活躍していた人物です。
しかし彼は、芸人という立場にとどまらず、絵本作家、映画監督、ビジネスクリエイターとしての道を次々に切り拓いていきました。
その過程では、常識外れの行動や発言が批判されたこともありました。
「テレビから逃げた」「芸人を辞めた」「調子に乗っている」――そんな声を浴びる中でも、西野さんは表現をやめず、信用を積み重ねながら挑戦を続けてきました。
たとえば、絵本『えんとつ町のプペル』は、分業制・クラウドファンディングという新しい手法で生まれた作品です。
さらに映画化、ミュージカル化へと広がり、「ディズニーを超える」と宣言するほどの大きなビジョンに挑み続けています。
彼の人生は、“挑戦”と“逆風”の連続でした。
だからこそ、卒業式という門出の場で「挑戦しろ」と語る言葉には、重みがあります。
「失敗を受け入れて、過去をアップデートし、試行錯誤を繰り返して成功に辿りついた時、
あの日の失敗が必要だったことを僕らは知ります。」
このスピーチには、「挑戦こそが人をつくる」という、彼自身の生き様がそのまま詰まっているのです。
要点①「未来は変えられなくても、過去は変えられる」
スピーチ終盤、西野さんは静かにこう語りかけました。
「僕たちは今この瞬間に未来を変えることはできない。
でも、過去を変えることはできる。」
この一節は、ただの言葉遊びではありません。
「過去は変えられない」と思われがちな中で、「変えられるのは過去だ」と逆説的に語ることで、聴く人の思考を一気に揺さぶります。
ここで西野さんが言う“過去を変える”とは、起きた出来事そのものではなく、「その出来事の意味づけを変える」ということです。
たとえば…
- 登場演出に失敗した → 笑いを取るきっかけになった
- 相方がバカだった → エピソードトークの宝庫になった
- 石田くんがスベった → 卒業式で語られる伝説になった
こうした“やらかし”や“恥ずかしい体験”も、見方を変えれば「ネタ」になり、「味わい深い物語」になります。
「過去をネタにしてしまえば、あのネガティブだった過去が俄然、輝き出す」
これは、西野さんの芸人としての強さでもあり、人生の教訓でもあります。
私たちもまた、過去の失敗や後悔を抱えながら生きています。
でも、それをどう捉え、どう語るかで、過去の価値は変わっていくのです。
そしてビジネスでも同じことが言えます。
- 提案が却下された経験
- プレゼンで噛んでしまった場面
- うまくいかなかったプロジェクト
こうした出来事を「失敗」としてしまうのか、それとも「今の自分をつくった経験」として語り直せるか。
その違いが、次の一歩に立ち向かうエネルギーになるのです。
要点②「失敗は存在しない。その瞬間に辞めるから“失敗”になる」
このスピーチで最も有名なフレーズ、それがタイトルにもなっているこの言葉です。
「失敗した瞬間に辞めてしまうから失敗が存在するわけで、
失敗を受け入れて、過去をアップデートし、試行錯誤を繰り返して成功に辿りついた時、
あの日の失敗が必要であったことを僕らは知ります。
つまり、理論上、この世界に失敗なんて存在しないわけです。」
この一言に、すべてが詰まっています。
誰もが「失敗が怖い」と思っています。
ですが、西野さんは「その失敗に“意味”を持たせないまま、辞めてしまうから“失敗”になる」と断言します。
たとえうまくいかなかったとしても、その経験がのちに成功につながれば、それは“必要な過程”になります。
つまり、挑戦を途中でやめない限り、それは「失敗」ではなく「成長の材料」だというわけです。
ビジネスに置き換えて考えてみると…
- 新しい企画が通らなかった
- 商品が売れなかった
- プレゼンでスベった
その瞬間は落ち込みますが、もしその経験を糧に改善を重ね、後に成果に結びついたなら——
それは「失敗」どころか、「勝ち方を学ぶ過程」だったことになります。
「途中で辞めなければ、すべては成功に繋がるプロセスになる」
この発想は、何かに挑戦するすべての人にとって、大きな支えになるのではないでしょうか。
そして何より、失敗を恐れて立ち止まってしまう人にとって、この言葉は背中を押す最初の一歩になるはずです。
要点③「鐘が鳴る前は報われない時間がある」
スピーチの最後に、西野さんは自身が手がける絵本『チックタック 約束の時計台』を引用しながら、こう語りかけます。
「時計の針って面白くて、長針と短針が毎時重なるんだけど、
11時台だけは重ならない。
二つの針が再び重なるのは12時。鐘が鳴る時です。」
ここで語られる“11時台”とは、がんばっても報われない時間のこと。
努力しても評価されない。挑戦しても結果が出ない。誤解される。叩かれる。
そういう“耐える時間”の象徴です。
「鐘が鳴る前は報われない時間がありますよ。
僕にもありましたし、皆さんにも必ずあります。
人生における11時台が。」
しかし彼は、こうも言い切ります。
「でも大丈夫。時計の針は必ず重なるから。」
この言葉には、未来への確かな信頼があります。
“今がうまくいかない時期”だとしても、それは時計でいえば11時台。
やがて針は重なり、鐘が鳴る。つまり、報われる瞬間は必ずやってくるというメッセージなのです。
ビジネスにおける「11時台」とは?
- 頑張っても結果が出ない期間
- 提案しても通らない日々
- 自分の努力が見えづらい環境
そういうときほど、「これでいいのか」「もうやめた方がいいのか」と迷います。
でも、「11時台だからこそ、まだ続ける意味がある」
そう思えることで、心が少し軽くなるはずです。
このスピーチの締めくくりは、単なる“励まし”ではなく、挑戦を続ける人へのエールであり、信じる力そのものでした。
ビジネスへの応用:笑われる挑戦こそ、未来をつくる
西野さんのスピーチには、終始一貫して「挑戦せよ」というメッセージが流れていました。
しかもそれは、「確実に成功しそうな挑戦」ではありません。
むしろ、鼻で笑われるような挑戦こそが、本当の価値を生むと語っているのです。
「小さな挑戦から、世界中に鼻で笑われてしまうような挑戦まで。
皆さんにはたくさんの時間があるので、たくさん挑戦してください。」
この言葉は、「今のままじゃダメだ」と思いながらも動けない人や、周囲の目が気になって踏み出せない人にこそ届くべきものだと感じます。
「挑戦し続けた人だけが、過去を“語れる過去”にできる。」
この言葉を、ビジネスの現場で、人生の節目で、何度も思い出したいと思います。
まとめ:挑戦し続ける人は、最後に“語れる過去”を手に入れる
キングコング西野亮廣さんが近畿大学の卒業式で語ったスピーチは、笑いあり、毒あり、でも最後に残るのは、本気のエールでした。
「失敗した瞬間に辞めてしまうから失敗が存在する。
でも、続ければ、それは“必要だった時間”に変わる。」
この言葉は、今まさに挑戦しようとしている人、あるいは“挑戦してうまくいかなかった経験”を抱えている人にとって、何よりの救いになるのではないでしょうか。
“笑われること”を恐れず、
“報われない時間”を受け入れ、
“意味づけを変える力”を信じて生きる。
西野さんのスピーチは、そんな挑戦者のためのメッセージでした。
そしてそれは、学生だけでなく、私たち社会人にも響くものです。
正解がない時代だからこそ、「理論上、失敗なんて存在しない」という言葉を信じて、今日からまた、自分なりの一歩を踏み出してみませんか?
誰かに語れる“過去”をつくるのは、今ここから始まる、あなた自身の“挑戦”です。