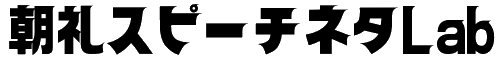さつまいも
皆さん、おはようございます。
秋が深まり、朝晩はぐっと冷え込むようになってきましたね。
通勤途中に金木犀の香りがふわっと漂ってくると、「ああ、秋だなあ」と感じる今日この頃です。
さて、そんな秋に旬を迎える食材のひとつが、さつまいもです。
焼き芋やスイートポテト、大学芋など、さつまいもを使った料理は、ほっこりとした甘さで私たちの心も体も温めてくれますよね。
実はこのさつまいも、かつて日本の人々を飢えから救った「命の食材」だったことをご存じでしょうか。
さつまいもが日本に初めて伝わったのは、江戸時代初期のことです。
1605年、沖縄の北谷町に住んでいた野國總管(のぐにそうかん)という人物が、中国から持ち帰ったのが始まりだとされています。
当時、沖縄は度重なる台風や天災に悩まされており、安定した食糧の確保が大きな課題でした。
野國總管は、気候や土地に合った作物を求めていた中で、さつまいもに注目したのです。
そして実際に栽培してみると、台風などの被害にも強く、痩せた土地でも育つうえに、収穫量も多い。この特性が、人々の命を支える大きな力となりました。
さらに忘れてはならないのが、儀間真常(ぎましんじょう)という人物の存在です。
彼は、野國總管とともにさつまいもの栽培技術を広め、沖縄全土にその価値を伝えました。
二人の努力によって、さつまいもは鹿児島を経由して本州へと広まり、日本各地で飢饉対策の一環として栽培されるようになったのです。
このように、今では当たり前のように食べているさつまいもにも、実は深い歴史と人々の思いが込められているのです。
沖縄県内の小学校では、今も彼らの物語が児童劇として語り継がれているそうで、郷土の誇りとして大切にされています。
私は、こうした背景を知ると、ひとつひとつの食材にも感謝の気持ちが湧いてきます。
ただ美味しいから食べる、というだけでなく、「この食べ物がどうやってここに届いたのか」という視点を持つと、日々の食事にも新たな意味が生まれるように思います。
ビジネスの世界でも、普段当たり前のように使っている道具や仕組み、サービスには、必ず誰かの努力や工夫、そして思いが込められているはずです。
そういった背景に目を向けることで、物事の価値やありがたみを再確認できるのではないでしょうか。
これから寒さが増していく季節です。温かいさつまいも料理を味わいながら、ほんの少し、そんな歴史や人の思いに想いを馳せてみるのも、豊かな時間の過ごし方ではないかと感じています。
今日も一日、よろしくお願いいたします。
しっくりくるスピーチが見つからない方へ
テーマを入力するだけで、あなただけのスピーチを作成してくれるツール「AIスピーチジェネレーター」を作成しました。
もう原稿作りに悩まない。AIスピーチジェネレーターは、あなたのアイデアを言葉に変える相棒です。
まだベータ版ですが、今なら誰でも無料・登録不要でお試しいただけます!