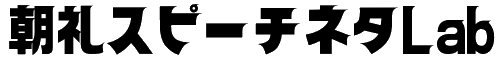世界絵文字デー
皆さん、おはようございます。
本日は7月17日、「世界絵文字デー」です。
この記念日は、iPhoneのカレンダー絵文字に表示されている日付が「7月17日」であることに由来しており、2014年にApple社が提唱しました。
現在では、世界中の企業や団体が絵文字の文化を称える日として、毎年さまざまな発表やイベントが行われています。
絵文字というと、LINEやメール、SNSなどで使われる、あの小さなアイコンを思い浮かべる方が多いと思います。
日々、何気なく使っているこの絵文字、実は日本発の文化であることをご存じでしょうか。
1999年、当時27歳だったドコモの社員、栗田穣崇さんが、わずか12×12ピクセルの極小アイコン176個を生み出しました。
彼が目を付けたのは、「文字だけでは感情が伝わりにくい」という課題でした。
ポケベル時代、若者たちがハートマーク一つで気持ちを伝えていたのを見て、彼は「感情をビジュアルで補完する」という、画期的なアイデアを具現化したのです。
この最初の絵文字たちは、iモードというドコモのサービスに組み込まれ、日本中で爆発的に広まりました。
それは単なる技術的な機能ではなく、新しい文化の誕生でした。
表情や天気、食べ物、記号など、あらゆるものを点の組み合わせで表現した絵文字は、人の心をつなぐ新たな言語になったのです。
しかし、絵文字の世界的普及にあたっては、もう一つ大きなストーリーがあります。
日本の通信キャリア各社が独自絵文字を開発し、互換性のない「絵文字戦争」とも言える混乱期を経て、2008年、AppleとGoogleがUnicodeという国際規格に絵文字を組み込む提案をしました。
これにより、2010年には絵文字が国際標準に採用され、「Emoji」として世界共通語となりました。
残念ながら、その標準化のプロセスで、ドコモはリーダーシップを取ることはできませんでした。
ドコモは独自の絵文字にこだわり続け、その結果、時代の流れに取り残される形となりました。
そしてつい先日、2025年5月、ドコモはついに「ドコモ絵文字」のサービス終了を発表しました。
これは、ただ一つの機能が終わったという話ではありません。
日本の技術と創造力が、どのように世界を変え、そしてどのようにしてその役割を終えたかという、壮大な物語の幕引きでもあるのです。
とはいえ、栗田さんが作った12×12の絵文字たちは、今もニューヨーク近代美術館に永久保存され、世界の文化遺産として残っています。
形は変わっても、本当に価値あるものは、人々の記憶と心の中に残り続けるのだと思います。
今日、私たちが送る一つのメッセージにも、誰かの心を和らげたり、笑顔を生んだりする力があるかもしれません。
小さな絵文字が世界を変えたように。
それでは今日も、笑顔の一日になりますように。
ありがとうございました。
しっくりくるスピーチが見つからない方へ
テーマを入力するだけで、あなただけのスピーチを作成してくれるツール「AIスピーチジェネレーター」を作成しました。
もう原稿作りに悩まない。AIスピーチジェネレーターは、あなたのアイデアを言葉に変える相棒です。
まだベータ版ですが、今なら誰でも無料・登録不要でお試しいただけます!