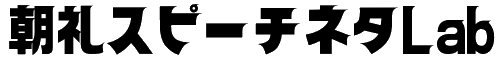ユニバーサルデザイン
皆さん、おはようございます。
春らしい穏やかな気候の中で、本日から始まった大阪・関西万博は、まさに未来を体験する場として、各方面から注目を集めています。
今回の大阪・関西万博では、国内外から訪れるあらゆる人々が快適に過ごせるよう、多くの場面でユニバーサルデザインが採用されています。
たとえば、会場内の誘導サインは文字だけでなくピクトグラムや音声案内を併用し、車椅子の方でも移動しやすいスロープや、点字ブロック、段差のない構造などが随所に取り入れられています。
こうした配慮の積み重ねが、「誰にとってもやさしい空間」をつくっているのです。
そしてこの姿勢は、「相手の立場に立って考える力」を象徴しているように思います。
誰かの困りごとを想像し、それを事前に解消する工夫をする。
これは、まさに“おもてなし”や“思いやり”の実践です。
ユニバーサルデザインというと、特別な設備や大きな予算が必要な印象を持たれるかもしれません。
でも、私はむしろ「気づくこと」「思いやること」から始まるものだと感じています。
たとえば、オフィスの会議室で資料を共有するとき、色の識別が難しい人にもわかりやすい配色にする。
エレベーター内で案内する声のボリュームを調整する。
あるいは、「わかりにくいかもしれないから、補足を入れておこう」といった一言も、ユニバーサルデザインの一部と言えるでしょう。
私たちの働く環境でも、さまざまな人がいます。
世代、国籍、経験値、性格、価値観。
そのすべてに“正解”を合わせることはできないかもしれませんが、「一人でも多くの人が快適に働ける場を目指す」姿勢は、組織全体の強さにもつながっていくのではないでしょうか。
万博会場の細かな工夫を見て、「ここまで気を配っているのか」と感じると同時に、「自分のまわりでは、どうだろう?」と振り返るきっかけにもなります。
私たちができる身近な配慮は、たとえば「その一言、誰かを置き去りにしていないか」と立ち止まって考えること。
そして、その小さな気づきを行動に移すこと。
ユニバーサルデザインとは、設備や建築の話にとどまらず、人と人との関わり方そのものを見直す視点なのだと、私は思います。
今回の万博を訪れる人々の笑顔の背景には、そうした“目に見えにくい心配り”が息づいています。
私たちも、日々の仕事や生活の中で、小さな配慮を積み重ねながら、誰もが心地よく過ごせる環境づくりを意識していけたらと思います。
ご清聴、ありがとうございました。
しっくりくるスピーチが見つからない方へ
テーマを入力するだけで、あなただけのスピーチを作成してくれるツール「AIスピーチジェネレーター」を作成しました。
もう原稿作りに悩まない。AIスピーチジェネレーターは、あなたのアイデアを言葉に変える相棒です。
まだベータ版ですが、今なら誰でも無料・登録不要でお試しいただけます!