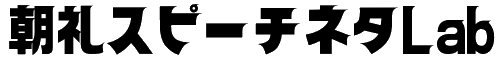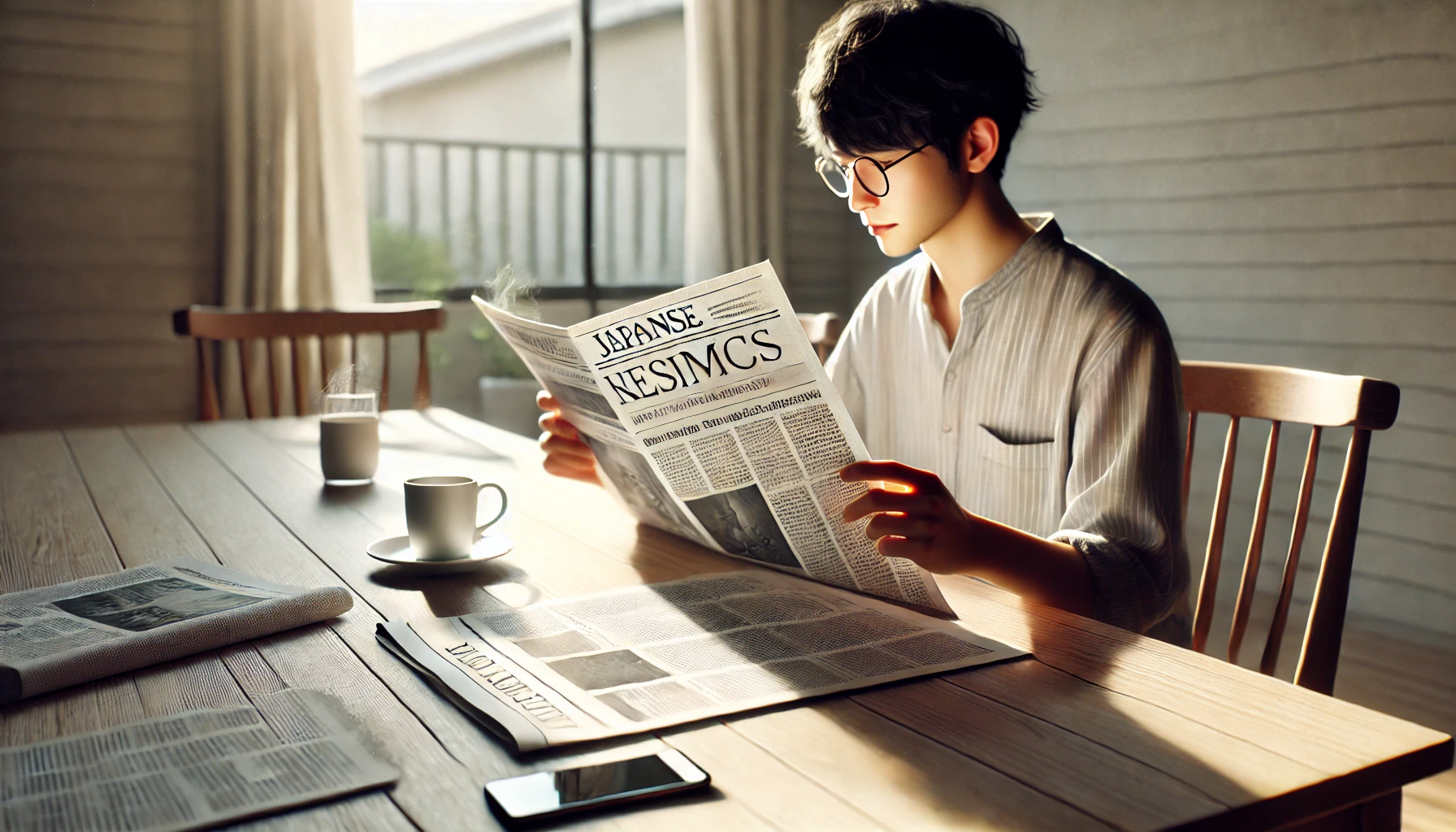新聞を読む日
皆さん、おはようございます。
春の空気もずいぶんと穏やかになり、通勤途中に新しいランドセルを背負った子どもたちを見かけると、自然とこちらも新鮮な気持ちになりますね。
さて、本日4月6日は「新聞を読む日」とされています。
語呂合わせの記念日ではありますが、「読む」という行為についてあらためて考えてみる、良いきっかけになる日だと思います。
最近では、紙の新聞よりも、スマホやSNS、ニュースアプリなどを通じて情報を得ることの方が主流になりつつあります。
私自身も、毎朝新聞を広げるというより、スマートフォンでニュースをざっとチェックすることの方が多くなりました。
しかし、その一方で、「本当に必要な情報を、自分の頭で選ぶ」という力が、今ほど問われている時代もないと感じます。
情報は、量の多さだけで価値が決まるものではありません。
むしろ、情報過多の現代においては、「何を知っているか」よりも、「何を信じて、どう活かすか」の方が重要なのだと思います。
新聞というメディアは、たとえば記事の構成や見出し、論説の書き方ひとつ取っても、「情報をどう伝えるか」を非常に慎重に設計しています。
時間をかけて取材し、裏付けをとり、第三者の目を通して公開される情報には、やはり一定の信頼性とバランスがあります。
その意味で、たまには意識的に新聞を読んでみるのもおすすめです。
一面的な意見ではなく、多様な視点から物事をとらえる練習にもなりますし、自分の思考のクセにも気づくことができます。
ビジネスの世界でも、情報をどう読み解くか、どのように判断材料として使うかは極めて重要な力です。
会議資料の裏にある数字の意図、取引先の発言の背景、市場ニュースの影響――それらを正確に把握するには、表面的な情報だけでは不十分です。
だからこそ、「読む力」と「考える力」をセットで養っていく必要があるのではないでしょうか。
今日は「新聞をヨム日」にちなんで、自分が最近触れている情報に少し意識を向けてみるのも良いかもしれません。
情報をただ受け取るのではなく、「これは自分にとってどんな意味があるのか?」と問いかけながら読む。
その小さな習慣の積み重ねが、判断力や洞察力として必ず役立つと、私は思っています。
しっくりくるスピーチが見つからない方へ
テーマを入力するだけで、あなただけのスピーチを作成してくれるツール「AIスピーチジェネレーター」を作成しました。
もう原稿作りに悩まない。AIスピーチジェネレーターは、あなたのアイデアを言葉に変える相棒です。
まだベータ版ですが、今なら誰でも無料・登録不要でお試しいただけます!